麻雀初心者の皆さん、最近麻雀に興味を持ち始めた方や、全くの未経験者も多いと思います。
麻雀は運だけでなく、戦略や技術も必要な奥深いゲームで、仲間と楽しく遊ぶのにぴったりなボードゲームです。
初めてプレイする際には覚えることが多く感じるかもしれませんが、安心してください。この記事では、一つ一つの手順を丁寧に解説し、あなたの麻雀体験を応援するための情報をたっぷりと詰め込んでいます。さあ、あなたも麻雀初心者から一歩踏み出し、この楽しいゲームの世界に飛び込んでみましょう!
知っておくべき基本ルールと用語
麻雀を始める前に、まずは基本のルールや用語をさっと押さえておきましょう。初心者が知っておくべき情報を解説していきます。
ルールを理解するための基礎知識
麻雀の基本を理解するためには、役や流れを把握することが不可欠です。
まず、麻雀の目的は「アガリ」、つまり役を作って点数を得ることです。参加者は各自配られた牌をもとに、捨て牌や鳴きを利用して、好きな役を作り上げます。
通常、144枚の牌を用いるため、その種類も多岐に渡ります。さらに、「ドラ」と呼ばれる特別な牌を意識することで、一気に高得点を狙える手段となります。
麻雀の進行方法:配牌からアガリまでの流れ
麻雀の進行は、配牌、ツモ、捨て牌、そしてアガリと、順調に流れます。
最初に、各自は牌を13枚受け取ります。この時点で、役を作る頭の体操が始まります。各自の番が来ると、山から1枚を引き手札を整え、1枚を捨てます。これが麻雀のサイクルです。
ゲームが進むにつれて、プレイヤー同士の読み合いが始まり、牌の動きが非常に緊迫感を持って行われます。この流れの中で、誰かが役を成立させると「ロン!」もしくは「自摸!(ツモ)」と言い、アガリになり、高得点を得るチャンスをつかみます。
ちなみに「ロン」とは、他の人が捨てた牌で役が完成し、アガリになった時に言い、「ツモ」は自分の番に引いた牌で役が完成し、アガリになったときに言います。
初めての人は、まずはこの流れを体験し、感覚を掴んでみましょう。
基本的なアガリの形
麻雀の基本的なアガリの形は「4面子1雀頭」です。
面子(メンツ)とは、3枚1組の牌の組み合わせです。123や678など数字が連続した3枚を『順子』(シュンツ)といい、666や東東東など同じ牌が3枚あるものを『刻子』(コーツ)といいます。
雀頭(ジャントウ)とは、66や東東など同じ牌が2枚の組み合わせです。
そのため、4面子1雀頭とした場合、14枚の牌を使用してアガリの形を作ります。
例外として、『槓子』(カンツ)と呼ばれ同じ牌4枚の組み合わせで面子扱いとなるものや、『七対子』(チートイツ)と呼ばれ雀頭7組でアガリとなるものもありますが、今は覚えなくていいでしょう。
牌の種類と読み方を覚える
麻雀の牌は大きく分けて「数牌」と「字牌」の2種類があります。
数牌は1から9の数字が書かれた牌で、さらに「筒子」(ピンズ)「索子」(ソーズ)「萬子」(マンズ/ワンズ)の3グループに分けられます。
一方、字牌は「風牌」と「三元牌」に分かれています。風牌は、東・南・西・北 の4種類、三元牌は白・発・中の3種類です。
初めはグループ分けが難しいかもしれませんが、牌を持ちながら何度も読み返すことで、覚えやすくなりますよ。
鳴きを覚える
麻雀には「ポン・チー・カン」という3種類の、”鳴き“というものがあります。
鳴くことで、「他の人が捨てた牌をもらう」ことができます。自分の力だけでは上がれない場合に相手の力を借りて自分の手牌をアガリに持っていきやすくなります。
・ポンとは、自分の手牌に雀頭があるときに、同じ牌を他の人が捨てた場合に鳴くことができます。どの人の捨て牌でも鳴くことができ、刻子を作ることができます。
・チーとは、鳴くことによって連続する数牌3枚(順子)が作れる時に使います。しかし、注意点としては左隣の人の捨て牌にしか鳴くことができません。3と5の2枚を持っている場合に左隣が4を捨てた場合でも345の順子を作ることができます。
・カンとは、同じ牌三枚の面子(刻子)が手牌にあるとき、それと同じ牌を他の人が捨てた場合に鳴くことができます。4枚1組ですが、扱いとしては面子(刻子)となります。自分で同じ牌を4枚引いた場合も同じくカンできますが、これは暗槓(アンカン)といい、鳴きにはなりません。
初心者の人は基本鳴かずに手牌を作ることを意識しましょう。
特にカンはタイミングや、メリット、デメリットがあるので、初心者の方は最初は覚えなくて大丈夫です。気になる方は別途詳しく紹介している記事がありますのでこちらをご覧ください!
初心者におすすめの麻雀役
麻雀を楽しむには、役の理解が肝心です!役を覚えることで、ゲームがより楽しくなること請け合いです。では、初心者におすすめの3つの役を紹介します。
最初に覚えるべき麻雀役
麻雀には多種多様な役がありますが、初心者がまず覚えるべきは「立直」「役牌」「タンヤオ」の三つです。一つ一つ解説していきます!
「立直」と気を付けるべきこと
まず一つ目に押さえておきたいのが「立直」(リーチ)です。
言葉からも想像しやすいと思いますが、あと1枚で4面子1雀頭の形ができる場合のことを指します。その場合リーチと宣言し、牌を通常と異なる横向きで捨て、1000点棒を場に出します。
これだけで役となり、あと1枚を他の人が捨てる、もしくは自分で引いた場合アガリとなります。リーチして上がった場合はドラ表示牌の下の牌をめくり、裏どらを確認することができます。
気を付けるべきこととしては、
- 門前でなければリーチできない。
- リーチ後は手牌を変えることができない。
という点です。
門前(メンゼン)とは、先ほど説明したポン・チー・カンなどの鳴きをしていない状態です。つまり自分の引いた牌のみであと一歩となった場合のみしかリーチは出来ないので注意しましょう。
またリーチ後は自分のアガリ牌が来るまで引いた牌を捨てることしかできません。「こっちの方がいいかも。」と思っても入れ替えることはできないことを頭に入れておきましょう。
「役牌」と気を付けるべきこと
次におさえておきたいのが「役牌」(ヤクハイ)です。
役牌とは、白・発・中に加え、自風牌・場風牌があります。自風牌・場風牌については分からない方はこちらからご覧ください。
これは3枚集めただけで役になります。ちなみにポンをして鳴いて集めても役になるため簡単に形を作ることができます。自分の手牌に2枚あるときに他の人が捨てた場合は率先して鳴いていきましょう。
気を付けるべきこととしては、
- 自風・場風は変わるので間違えないようにする。
です。そのままの意味ですが、自風と場風は局ごとに変わります。上がる形を作るのが困難になってしまうので、間違えて意味のない牌を鳴かないようにしましょう。
「タンヤオ」と気を付けるべきこと
3つ目に紹介するのが「タンヤオ」です。
タンヤオとは、1,9,字牌なしの形のことです。つまり、数牌の2~8までで4面子1雀頭を作った場合につく役です。
順子・刻子どちらでも構わないので、チーやポンを使って簡単に作ることができる、麻雀の超基本となる役になります。
気を付けるべきこととしては
- アガリ牌も2~8の数牌であること。
- 雀頭も2~8の数牌であること。
があげられます。説明した通り、2~8までの数牌のみであることを頭に入れておけば、基本的に何も気を付けるべきこともありませんが、アガリ牌や雀頭にも1,9,字牌がないか注意してみましょう。
まとめと紹介
今回は麻雀を始めてみたいと思う人に向けて麻雀の流れや基本、簡単な役をまとめました。
「麻雀覚えること多いからやめようかな」と思ったあなた!まずはやってみてください!
詳しいところは携帯のゲーム、もしくは友達と遊びでながらでも、やり始めたら意外に覚えてくるものです。経験してみて面白いと思ったら自分からどんどん調べるようになってますよ(笑)
今回は麻雀を始めるための第一歩で超基本を説明しました。他にも次に覚えたいことや、役、おすすめの麻雀ゲームや漫画、アニメ、点数計算、麻雀のコツまでどんどん書いていきますので、ぜひチェックしてください!
一緒に学んで、麻雀を盛り上げていきましょう!!!

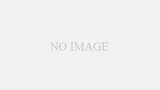
コメント